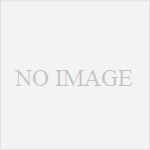【本】1973年のピンボール / 村上春樹
「1Q84」を読んで以来、村上春樹熱がこみ上げて来ているCheese。
今度は1980年に上梓された「1973年のピンボール」を読みました。
でも、なんというか…。
実は私は「1Q84」を読むまで「なんか村上春樹って、思わせぶりで知的っぽい会話と、意味不明な比喩、翻訳調の会話を駆使するだけの作家だよねー」と、思っていました。
その思い込みのもと、自意識過剰にも村上作品を避けてきていたのですが、この作品はまさに以前私が抱いてきたイメージぴったりの小説でした。
私は1974年生まれなので、1973年は生まれる1年前に当たるのですが、やはり自分の生まれるちょっと前の時代を描いた作品では、“同時代性” を感じることができないということなのでしょうか。。。
<STORY>
1973年、友人と起業した翻訳会社で翻訳の仕事をしながら自由に生きていた25歳の「僕」の家に、双子の女の子が住みつく。僕はふたりの正体を知ろうともしないままに、双子と一緒に気ままに暮らして行く。大学を卒業しだらだらと日々を送る「鼠」は、近所のバー「ジェイズ・バー」でバーテンのジェイと話したりピンボールをしながら生きていた。「僕」は姿を消したピンボールの機械に無性に会いたくなり、なんとか探そうとする…。
<感想>
うーん、上記のSTORYがどうにも意味不明…。
すみません、文章力が及ばなくて。
でも正直に言うと、この小説、「1973年のピンボール」、私にはよく理解できませんでした。
そりゃあ、理解できてない分際で要約なんてしても、人に伝わる文章なんて書けないですよね。
よくわからないなりに感じたことをつらつらと。
主人公は、どうして他者と深くコミットしようとしないのでしょうか?
前作「風の歌を聴け」で、直子と深くコミットしようとしたけれど、彼女が自分を置いて死んでしまったから?
それで、新しく出会う人やモノとも深く知りあおうとせず、自分のルールだけを貫いて生きようということなのでしょうか。
それとも、これは学生運動の影響なのでしょうか。
社会を変えよう、自分たちの力で社会を変えられる、という信念のもとに生きてきた世代は、自分たちの力なんて、結局は社会の前では何の役にも立たないと思い知らされ、厭世的に生きるしかないということ?
高度経済成長が終わった後に生まれ、自分たちの力で社会など変えられるわけがないと思いこんで生きている世代の私からすると、「僕」の感覚はよくわかりませんでした。
今、2010年を生きる35歳の女性である私から見ると、この主人公たちの生き方がかっこよかった時代はもう過ぎ去り、帰って来ないように思います。
2010年に25歳を生きている人たちの状況は、きっともっと深刻です。