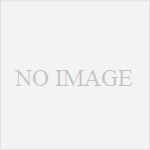【映画レビュー】ぼくを葬る / LE TEMPS QUI RESTE
入手したまま、ほったらかしになっているDVDの数々、そろそろ見ていかねば…。
ということで、今日はフランソワ・オゾン監督の『ぼくを葬る』を観ました。
余命3カ月と宣告されたゲイの青年の彷徨…。
私には、ゲイの男性が、“女性”と決着をつけ、運命を受け入れて行く道程に思えました。
でも、死を前にした人間がとる行動は、結局そこに行きつくんだろうか?
自らの死についてあんまり深く考えたことのなかった私ですが、この結末はどうもありきたりなパターンに思えたりも…。
<STORY>
31歳のフォトグラファー、ロマンは癌で余命3カ月を宣告される。休暇を取り、恋人とも別れ、一人暮らしを始めるロマン。両親や姉と食事をしても、ケンカ別れをしてしまう。姉ソフィーとは、幼い頃は仲が良かったが、今はお互いにうまくいかないのだ。誰にも病気を告げていなかったロマンだが、祖母ローラにだけは病気のことを打ち明ける。祖母の家から帰る途中、偶然出会った夫婦に「代理父にならないか」という提案を受けるのだが…。
<解説>
この映画を撮ったフランソワ・オゾン監督は、ゲイであることを公言しています。
本作の主人公のロマンは、オゾン監督が自分を投影したキャラクターだと言われています。
何度も出てくるモチーフは、仲の良かった頃、子供時代の姉・ソフィーと主人公の姿。
二人でいたずらをし、笑いあい、頬にキスをする無邪気な姉弟です。
幼い頃は愛し合い、仲の良かった姉弟が、大人になり、お互いにうまくいかなくなる…。
姉が、ゲイである弟を受け入れられなかったから?
弟が、他の男性に嫁いだ姉を許せなかったから?
仲互いの原因は描かれていませんが、幼いころいつも一緒にいて、愛し合っていた姉弟だからこそ、簡単に乗り越えられないほど大きな溝が出来てしまったのかもしれません。
その溝が修復されるのは、弟が自分の死を意識した時。
“死”を前にし、何かを受け入れるという大きな心境の変化によって、やっと、修復されるのです。
それだけの大きな代償を超えなければ、埋めることの出来なかった溝…。
オゾン監督の抱える大きな無常感が伝わってくるようです。
この物語には、3人の女性が重要な存在として登場します。
一人は姉のソフィー。
ロマンを愛し、赦す女性。
もう一人は祖母のローラ。
ロマンを理解し、死を共有する女性。
そして、ロマンに代理父になってくれと頼む、ジャニィ。
(子供の父親として)ロマンを必要とする女性。
ゲイとして好きに生きてきたロマンは、女性たちの愛と赦し、理解を得て、そして女性に必要とされることによって、自らの運命を受け入れることが出来たのではないでしょうか。
と、ついついそんな風に女性を重要なテーマと考えてしまうのは、私が女性だからですかね?
恋人・サシャや父親、ジャニィの夫らの扱いが、前述の女性たちに比べてえらくあっさりし過ぎてるように思えてしまったもので。。。
それにしても、死を前にした人間は、やっぱり自分の遺伝子を残したくなるものなのでしょうか?
その気持ちはわかることはわかるんですが、「そこに落ち着くかー」と、なんとなく残念な気がしました。
あれ、これってネタバレ?
でも、DVDのジャケ写にもなってるし、これくらいならアリだよね?
『ぼくを葬る』(81分/フランス/2005年)
原題:LE TEMPS QUI RESTE
英題:TIME TO LEAVE
公開:2006年4月22日
監督:フランソワ・オゾン
出演:メルヴィル・プポー/ジャンヌ・モロー/ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ/ダニエル・デュヴァル/マリー・リヴィエール
![ぼくを葬る [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/215HT9908DL._SL160_.jpg)